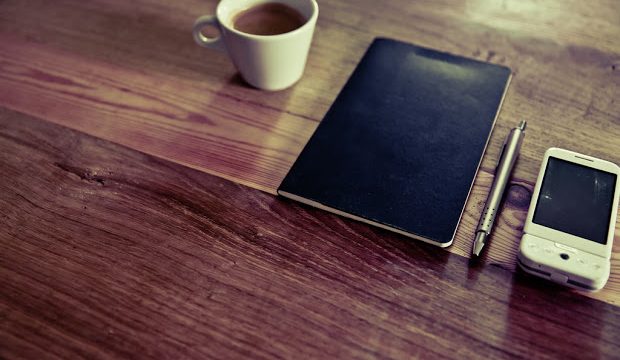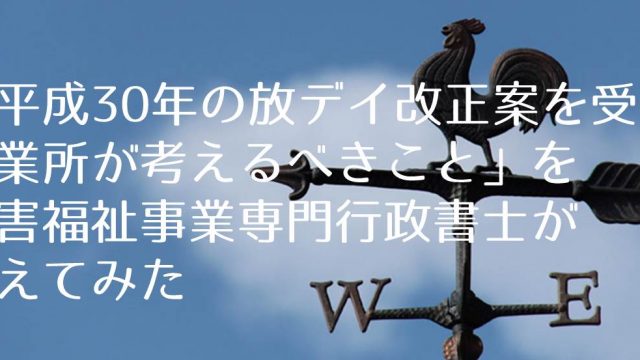「これまでは福祉の法律を現場職員に任せっぱなしで運営してきたけど、リスクが分かった。自分も理解したいが複雑でどこまで抑えたらいいものでしょうか」
書類整備ができているかどうかを点検しに伺った際に、このようなご相談を頂くことが増えてきました。
各現場を定期的に訪れて、スタッフの雰囲気や事故トラブルがないかは把握していても、専門知識を必用とする法律関係のことは、責任者に任せているという運営方法をとる事業者様も多いです。
スタッフを信じて託せているという点では望ましいことですが、書類点検にお伺いすると現場スタッフの経験、努力に頼っていたためにおこる不備もしばしば見受けられます。
もちろん十分に事業者ハンドブックや官公庁への問い合わせなどを通して細かに理解して、こちらがびっくりするくらいきっちりとした運営をする事業者様もいますが、どちらかというとレアケースです。
施設数が増えて、代表が全ての事業所を見て回ることが難しくなるにしても以下のポイントは抑えておくことが望ましいです。
- 毎月ごとに、人の配置(シフト)は各事業において定められている許可基準を満たしているか
- 算定している加算の条件は、きちんと満たしたうえで事業運営を行えているか(シフト、書類整備など)
- 利用者の支援計画は、サビ管・児発管の名のもと、各事業において定められている最低限の更新頻度で運用されているかどうか
たとえオーナー型の経営者で、運営の一切は管理者・サビ管などに任せているにしても、最低限これらのポイントは各施設の責任者の報告を理解できるくらいには抑えておくことが望ましいです。
大規模な返金などがあっても現場のスタッフでは責任をとれません。
今回お伝えしたような最低限のポイントは抑えて、スタッフと連携できる体制を作っていくことが適正な事業運営、事業規模をスケールさせるためには不可欠だと考えます。
本項が貴社の事業運営の参考になれば幸いです。
前回のコラムはこちら

無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や重要情報の共有に使用しております。
お問い合わせはこちら
業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は
以下のページからお受けしております。